病気休職中に最初に読んだ本は「休職と復職の教科書」
病気休職中に最初に読んだ本は、武神健之「未来のキャリアを守る 休職と復職の教科書」です。
きっかけはYouTube。「休めない自分」に気づかされた言葉
この本を読もうと思ったきっかけは、たまたまYouTubeのおすすめ出てきた以下の動画を見たことです。
このYouTubeの冒頭にあるように、
- 休職が決まったときに、休職中の計画を立てる人がメンタル不調になる人では多い
- だらだらすることが休職する人は一番不得意
といったことを見て、まさに私だ!と。
「休職は甘え?」罪悪感と焦りでいっぱいだった日々
私の場合は、内科医の診断で休職期間が1ヶ月でしたが、心もズタボロ…自己判断で適応障害なのでは?とも内心思っていました。
休職期間も1週目はとにかく体を休めて、2週目からは学校に戻ったときに余裕ができるように、教材研究を進めたり、通知表の所見メモを書いたりしよう!なんて考えていました。また、母や友人は毎日仕事に行き、朝から晩まで働いているし、クラスの子供たちだって頑張って勉強しているはずなのに…私はこんなことをしていていいの?と。
ちょうどその頃は、実家に帰っており、定年退職した父が家にいてご飯を作ってくれたり、話を聞いてくれたりと身の回りの世話をしてくれていました。父は現役時代、ずっと休まず家族のために働いてくれていたのに…私はまだ若いし、体調は悪いけど体だって動かせるのに、家族の役に立つわけでもなく、迷惑も心配もかけてしまっていてなんて親不孝なのだと。毎日罪悪感を抱いていました。
「自分はもっと頑張れなかったのか?」、「メンタル不調は甘えなのかも」と休職期間に入っているのにも関わらず、何も考えずにダラダラすることはなかなかできませんでした。
心に刺さり、背中を押してくれた産業医の言葉
でも、この動画を見て、
- 人って変わらない、他人は変わらない、変えることができるのは自分だけ。
- メンタル不調の人は何を言われてもネガティブに受け取る。
といったことがグサグサと自分の心に刺さりました。
その中でも特に
- メンタル不調になる人は、弱いとは思わない。たまたまなってしまった。仕事を辞めれば治る。
- 真面目だから、責任感が強いから。恥じる必要はまったくない。
といった場面では勇気づけられました。
母にも「自分がもし癌になってしまって休んでいるのならば、そんなに自分を責めないでしょう?仕方がないことだから考えずに休んでいいのよ」と言われていました。でも、家族だからそんなふうに言ってくれるのだと思っていたところもあり、産業医の先生が話しているのを見ると、説得力を感じました。お医者さんと同じように励ましてくれた母、素晴らしい!笑
この人が書いた本ならば、自分にとってショックなことはきっと書いてないだろう、安心して読めると思い、その日のうちにamazonで注文しました。
実際に本を読んで得られた、一番大きな「気づき」
実際に読んでみると、
- 症状について
- 実際の患者さんのケース
- 復職までの期間の過ごし方
が詳しく書いてあったので、自分と重ね合わせながら共感し、納得もしました。
また、メンタル不調になったことがある人は、「今後職場で同じような人の気持ちを理解できるので、集団にとって大切な存在である」と書かれており、おこがましいかもしれませんが、どこかで再就職した際にはぜひ周囲の力になれるようにしよう!と思いました。
また、この本を読んでみて、もっとも印象に残ったのは、仕事以外のリフレッシュできる環境や趣味をもつことがいかに大切であるかということです。仕事で嫌なことがあっても、その気分を切り替えたり、解消できたりする自分の好きなことを見つけること。
私には「好きなこと」がない? 新たな課題との出会い
今思えば私は、それがまったくできておらず、家でも教材研究をしたり、クラスの気になるあの子への良い言葉がけを考えたりと常に仕事のことで頭がいっぱいでした。それが、本当に好きなことなら良かったのですが、夏休み期間などの長期休みになるとホッとし、進んでしたいとは思えていなかったので…自分の中でも多少苦痛を感じながらも、カフェで教材研究をやって楽しい気分にさせるなどごまかしながらやっていたのだと思います。
みなさんには、好きなことってありますか?
ここで、すぐにこれ!と言える人、私からするととてもうらやましいです。まだまだ探し中ですが、最近はお掃除や料理をすると気分がよくなるので地味だけどこれが趣味?なんて考えたり、家事をまた楽しいとごまかしてる?なんて少し疑いながらもやっています(笑)
まとめ:休職に関わるすべての人に読んでほしい一冊
話がそれましたが、この本は表紙の帯にもあるように、「メンタル不調で休む前に知っておきたかったこと」「人事・上司・家族も必見!」だと私も思うので、気になった方はぜひ!
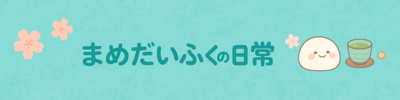



コメント